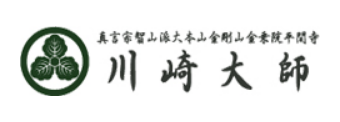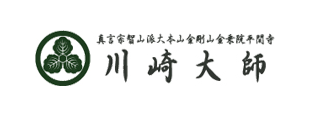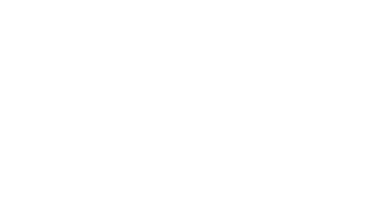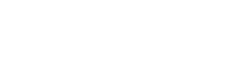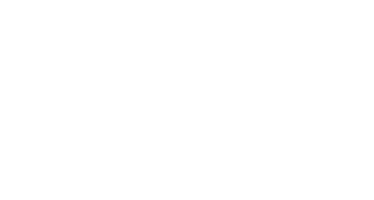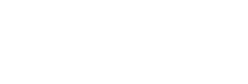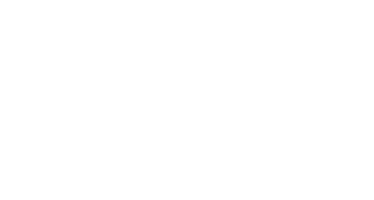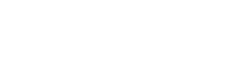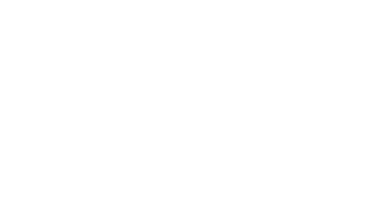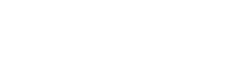聖観音年祭
(しょうかんのんねんさい)
令和7年5月1日(木)
10:00~ 聖観音尊像前
聖観音像は、帝室技芸員・鈴木長吉師作、帝国ホテル初代料理長・吉川兼吉氏の寄進により明治36年(1903)に造立。平成29年(2017)川崎大師開創890年記念事業「日本百観音霊場お砂踏み参拝所」開設にあわせて鶴の池ほとりに移設奉祀されました。
5月1日、聖観音さまの年祭法要が執り行われます。


川崎大師子どもフェスタ
(かわさきだいしこどもフェスタ)

ミニSL乗車会
子育満足・学業成就・身上安全 柴燈大護摩供大祈祷会
(さいとうおおごまくだいきとうえ)
令和7年5月4日(日・祝)
13:00~ 祈りと平和の像前(大山門入って左)
修験者(山伏)が野外で行う護摩祈祷、柴燈大護摩供が執り行われます。修験者による修法の後、道場中央の炉壇に点火されると、白煙とともに大きな炎が立ち昇ります。
法要では、諸願成就を祈願してご自身の手で炎に投じる「なで木」のお焚き上げ、火渡り修行に参加いただけます。
お子さまもご参加いただけます。
荒天等にて中止の場合は、7月の塩原温泉厄除不動尊年祭法要にて御祈願いたします。
○「なで木」奉納のご案内
柴燈大護摩供では「なで木」を浄火に投じてお焚き上げし、諸願成就を祈願します。ぜひこの機会に「なで木」をご奉納くださいますようご案内申し上げます。
| 頒 布 金 | 「なで木」1本 500円 お名前とお願いごとを記入してご奉納ください。 |
|---|---|
| 頒布期間 | 令和7年5月4日(日・祝)まで ※法要当日まで頒布しています |
| 頒布場所 | 奉納護摩木所、信徒会館ステンドホール受付 薬師殿、自動車交通安全祈祷殿 |

柴燈大護摩供

ご信徒による「なで木」の投入

火渡り修行

なで木
川崎大師薪能
(かわさきだいしたきぎのう)
令和7年5月13日(火) 17:30~
川崎の初夏の風物詩・薪能が開催されます。
チケット情報


| 日 時 |
令和7年5月13日(火)17:30開演 |
|---|---|
| 会 場 |
川崎大師平間寺 特設舞台(雨天時:川崎大師信徒会館) |
| 前 売 入場券 |
・SS席10,000円 (正面1・2列目指定・区分内自由、雨天時 信徒会館入場可) ・S席7,000円 (区分指定・区分内自由、雨天時 信徒会館入場可) ・A席4,500円 (区分指定・区分内自由、雨天時 払い戻し) ・U25(A席)2,000円 (25歳以下の方、未就学児を除く。入場時に年齢が分かるものをご提示ください。) ※A席、U25チケットは雨天時、信徒会館への入場はできません ※当山では、SS席、U25チケットは取扱いしておりません |
| 取扱い |
令和7年4月3日(木)10:00発売 ・チケットぴあ ・ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター ・川崎駅北口かわさき きたテラス観光案内所(※) ・川崎能楽堂(※) ・川崎大師平間寺(※) 「※」は窓口販売のみ。電話予約は受け付けておりません。 |
| 演 目 |
・薪能法楽 ・仕 舞 「西王母」 鵜澤 久 「経正」 岡本房雄 「小鍛冶」 鵜澤 光 ・狂 言 「宝の槌」 山本泰太郎 ・仕 舞 「笠之段」 山階彌右衛門 「玉之段」 観世清和 「鵜之段」 観世恭秀 ・ 能 「春日龍神龍女之舞」 観世三郎太 |
| お問合せ先 |
川崎市文化財団 川崎大師薪能係 TEL:044-272-7366(平日 9:00~17:00) 最新情報については、川崎市文化財団ホームページでご確認ください。 |

かがり火に火入れする当山貫首
御本尊弘法大師降誕奉祝会
(ごほんぞんこうぼうだいしごうたんほうしゅくえ)
令和7年5月18日(日)
11:30~ 大本堂
弘法大師空海上人は、宝亀5年(774)6月15日、現在の香川県善通寺市にご誕生されました。当山では、弘法大師空海上人の誕生を祝う降誕奉祝会を雨季の6月を避け、1ヵ月早めて執りおこないます。
当日は、大導師当山貫首を中心に檀信徒、日曜教苑苑児、幼稚園園児等によって表参道仲見世の練行列がおこなわれます。
静嘉堂石庭前において川崎大師奉納弓道大会が開催されます。

奉祝法要の様子
救世観音年祭
(くぜかんのんねんさい)
令和7年5月20日(火)
13:00 大護摩供に引き続き
大本堂
常に慈眼をもって衆生を見守ってくださる観音さまのお徳を讃える法要です。
この法要には、ご詠歌をお唱えする遍照講講員の方々が多数参列され、当山第44世・中興第1世貫首(隆天大和上)謹作の救世観音御詠歌が奉詠されます。
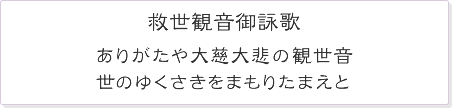

救世観音年祭
まり塚まつり
(まりづかまつり)
令和7年5月21日(水)
11:00~ まり塚碑前
まり塚まつりは、太神楽曲芸師が日頃高座で使用している「まり」や「ばち」等の道具に感謝し、芸道精進・発展を願う法要です。
当山の「まり塚」は、昭和26年(1951)に建立され、昭和35年(1960)に東京太神楽曲芸協会によって再建されたもので、法要当日は会員の方々が参列し、曲芸の道具などに感謝を込め供養が行われます。
この日、境内の特設舞台では、同協会会員によって昔懐かしい演芸の数々が奉納されます。

まり塚碑に献香・献花する参列者

東京太神楽曲芸協会会員による奉納演芸
二箇大法要
(にかだいほうよう)
令和7年5月21日(水)
14:00~ 大本堂
当山で1年に5回修行される特別な法要で、経文に曲調をつけて奉唱し、み仏の徳をたたえる「唄匿(ばいのく)」と華をまいてみ仏を供養する「散華」という2つのお経を中心とした法儀です。
大本堂内では大勢のご信徒が参列するなか、信徒安全・興隆仏法祈願の大護摩供の修行とともに、密教色豊かな格調高い法儀がつぎつぎにくりひろげられます。この法要のなかで僧侶が「香華供養仏」ととなえ、いっせいに華を散じ、その華がハラハラと舞うさまは、まさに法悦の境地といえます。

二箇大法要の盛儀

法要参列者には特別散華が授与されます
ご献茶式(宗徧流お家元勤仕)
(ごけんちゃしき)
令和7年5月25日(日)
10:30~ 大本堂
ご献茶式は、茶道宗徧流・山田宗徧お家元勤仕のもと、御本尊御宝前にお抹茶をお供えする儀式です。大本堂において、当山貫首大導師のもと大護摩供が厳修されるなか、特設のお点前座にてお家元によりご献茶の儀が勤められます。
この日、山内各所でお茶会が開かれ、宗徧流関係者、茶道愛好者は終日お茶を楽しまれます。また、境内には呈茶席が設けられます。

ご献茶式の儀を勤める茶道宗徧流 山田宗徧お家元

和やかなお茶会
大般若経転読会
(だいはんにゃきょうてんどくえ)
令和7年5月25日(日)
13:00~ 大本堂
大般若経とは600巻にもおよぶ唐の玄奘三蔵(三蔵法師)訳の大部の経典です。
大般若経転読会では大導師と12人の僧侶が経典を扇をひろげるがごとく空中にかざし、声高らかに経題が転読されます。

大般若経を転読する当山貫首